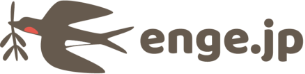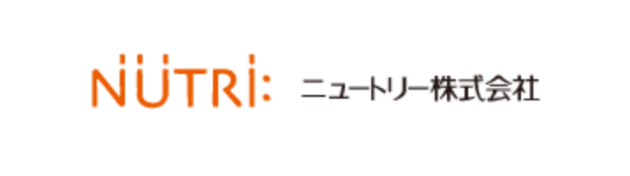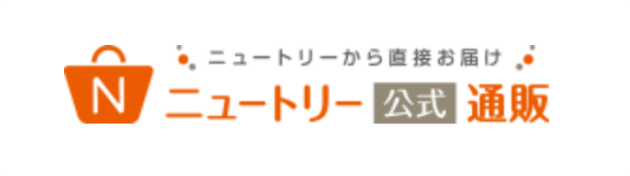最新Topics
\カムカムスワロー共催 見た目もおいしいえんげ食体験会 開催レポート/
嚥下食コースを堪能しながら学ぶ!摂食・嚥下専門家による最新トピックス

岐阜県岐阜市にある「カムカムスワロー」で、メニューのリニューアルを記念し「見た目もおいしい えんげ食体験会」が開催されました。医療・介護従事者を対象とした第2部では、進化した嚥下食を試食しながら、摂食・嚥下の専門家である朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 摂食嚥下リハビリテーション学分野 教授 谷口裕重先生と東北生活文化大学 家政学部 家政学科 教授 中尾真理先生から嚥下障害のケアや予防、低栄養対策や物性評価方法など、実演や実技を交えてお話しいただきました。会場の様子とあわせて講演内容をご紹介します。
五感で味わう“おいしい嚥下食”と、実践につながる学びの時間
2025年4月4日、近石病院が運営する地域のコミュニティスペース・カムカムスワローで「見た目もおいしい えんげ食体験会」が開催されました。医療・介護従事者を対象とした第2部では、フレンチ出身のシェフによってリニューアルされた嚥下食コースをワンプレートで提供しご試食いただきました。ワンプレートとはいえ、内容は本格的。第1部同様、鯛のカルパッチョ、ハンバーグをメインに、お粥、スープ、デザートまでそろった、色鮮やかな嚥下食に、会場では感嘆の声があがりました。参加者は、味や香りを楽しみながら、スプーンや舌で物性を評価していました。
試食と同時に、ゲストの朝日大学 谷口裕重先生、東北生活文化大学 中尾真理先生による講演がスタート。嚥下障害のケアや予防、低栄養対策や物性評価方法についてお話いただきました。

100歳まで美味しく食べる!従来の「三位一体」から「四位一体」の視点へ
谷口先生からは、摂食嚥下障害の現状に触れながら、これからのケアのあり方について解説いただきました。
これまでは、メタボリックシンドロームや過栄養が問題とされてきましたが、現在はむしろ、低栄養やフレイル(虚弱)、サルコペニア(加齢による全身の筋肉量の減少と筋力低下)といった問題が深刻化しており、摂食嚥下障害を抱える方が急増しています。「日本人の85歳以上では約25%が低栄養」というデータもあることから、“美味しくしっかり食べること”が高齢期の健康維持には欠かせません。さらに、栄養状態は筋肉量や筋力だけでなく、認知機能にも密接に関わっており、医療現場でも大きな課題となっています。
長く美味しく食べ続けるためには、重要なポイントが2つあります。1つ目は、全身機能と栄養、口腔、そして
“呼吸”を加えた「四位一体のケア」です。
BMI13と低体重で骨折してしまった方の事例では、明らかなサルコペニアと低栄養が疑われ、サルコペニアを起因とした嚥下障害がありました。深呼吸をしても胸が動かないほど胸郭が固くなっており、咳を出せない。呼吸機能が低下していると、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。また、こういった方は、口の中も痂皮(かひ)や痰などがあり、口腔機能の低下もみられます。このように、全身・栄養・口腔・呼吸は密接に関わっており、「四位一体」での介入が“食べること”を支えるのです。
参加者から「呼吸機能を向上させるには、何を行えばよいのか?」という質問が寄せられました。
谷口先生からは、「息を長く吐くこと」が有効であり、趣味のハーモニカが呼吸訓練として役立ったという実例もご紹介いただきました。さらに腹部を軽く押して補助することで息を吐きやすくなり、より効果的にトレーニングが行えるというアドバイスもありました。

摂食嚥下障害は予防ができる?!
“気づき”の重要性
かつては、脳血管疾患や神経筋疾患が主な原因とされていた嚥下障害ですが、近年ではサルコペニアを起因とした嚥下障害が増加しています。これを防ぐためには、2つ目のポイント「予防」が重要となります。
実は、“摂食嚥下障害は予防できる“という考え方が医療現場でも一般的になり、そうした背景をふまえ、「なってから対応する」のではなく、早期発見・早期介入し、悪化を防ぐことが重要です。
とはいえ、嚥下障害の原因は人それぞれ。だからこそ、全身・栄養・口腔・呼吸の「四位一体」の視点で、どこにリスクが潜んでいるかを見極め、早めにアプローチすることが求められます。たとえば、最近1年の間に転倒した経験がある方、歩くスピードが遅くなってきた方は、要注意です。医療・介護従事者の方々には、日々の関わりの中で、そうした小さなサインにいち早く気づき、「四位一体」の視点で早期の予防につなげていただきたい。——谷口先生はそう呼びかけていました。
講演の最後には、谷口先生がご自身の鼻に内視鏡を挿入し、食べ物を使って正常な飲み込みと、誤嚥した様子を実演。リアルタイム映像を使いながら解説いただき、参加者の理解が深まりました。
参加者からは「サルコペニアが嚥下障害を引き起こし、嚥下障害がまたサルコペニアを悪化させる。という悪循環になっていることがよく分かりました。100歳まで美味しく食べるためには、あらゆる視点での“気づき”が重要であることを学びました」との感想が寄せられました。

嚥下食で重要視される「安全性」と「食べる楽しみ」の両立
続いて「嚥下食の固さと付着性の選び方」をテーマに、中尾先生からご講演いただきました。
医療・介護従事者の方は、安全性を重視して嚥下食を提供する一方で、嚥下障害のある方にとっては、「好きなものが食べられない」という辛い経験につながることがあります。だからこそ、「安全性」だけでなく「食事の楽しみ」にも目を向け、両立を目指す必要があります。
そのためには、なぜ嚥下食が必要なのか、その背景や意味をきちんと理解した上で伝える姿勢が求められます。
嚥下障害には“さまざまなリスク”が存在します。実際に、嚥下障害は窒息や誤嚥性肺炎、低栄養などの原因となることが、研究結果から分かっています。
日本では年間約8,000人が窒息で亡くなっています。嚥下障害がない方でも窒息で無くなるケースはありますが、原因の多くは食べものによるもので、病院や施設で提供される“お粥”ですら、窒息の原因になり得るため注意が必要です。
また、嚥下障害は肺炎の原因にもなります。65歳以上の肺炎のうち約7割が「誤嚥性肺炎」と言われ、加齢に伴う身体機能の低下および嚥下障害が主な原因とされています。なお、誤嚥性肺炎は、2024年に初めて「成人肺炎診療ガイドライン」において「誤嚥のリスクがある宿主に生じる肺炎」と定義づけられ、誤嚥のリスクが明確に示されました。
栄養状態については、嚥下障害がある高齢者では、そうでない人に比べて約2倍、低栄養リスクが高まるとの報告があります。
こうしたデータからも分かるように、医療・介護従事者が嚥下食を提供する最大の目的は、嚥下障害のある方が窒息や誤嚥をせず安全に食事し、さらには低栄養を防ぐことです。そのためには、一人ひとりの嚥下機能に応じた食形態に調整しつつ、栄養価をしっかり確保した食事を提供することが求められるのです。

身近な道具で学ぶ!IDDSI(国際嚥下食標準化構想)ガイドラインにおける物性評価方法
さらに中尾先生からは、嚥下食を提供するうえで欠かせない物性評価のポイントについて、実践的な内容をお話いただきました。
食品は単に「やわらかければよい」というわけではありません。
たとえば、付着性の高い食品は、飲み込む時に舌や咽頭のたくさんの機能を必要とし、咽頭残留が多くなる傾向も報告されています。凝集性についても、ある程度まとまりがないと飲み込みにくくなり、逆に切れないほど凝集性が高くても適切ではありません。
このようなさまざま物性の嚥下食を分類し、共通言語化した「嚥下調整食分類2021※」が日本では用いられています。一方、国際的には「IDDSI(国際嚥下食標準化構想)」という基準があり、国が違っても共通の基準で食形態を理解するために策定されました。
IDDSIのガイドラインでは、フォークやスプーン、秤を使った、現場でも取り入れやすいシンプルな物性評価方法が紹介されています。
講演内では、参加者の皆さんにIDDSIの物性評価方法を体験していただきました。「スプーン傾けテスト」では付着性を、また「フォーク切りテスト」では凝集性ややわらかさを評価。さらに、舌でつぶせるかどうかを想定した「はかりを使ったフォーク押しテスト」では、キッチンスケールを使って物性を確認しました。
参加者からは「実際に評価方法を教えてもらえて、臨床でも役に立つと思います。今回学んだことを、利用者様に伝えていきたい」という声が聞かれ、学びを現場で活かしたいという前向きな姿勢がうかがえました。
「身近な道具を使って物性を確認できるようになると、外出先でも安心して食事を選べるようになり、行動の幅が広がります。病院や施設だけでなく、在宅医療現場でも活用できるので、様々な食品で試してみてください。」——参加者へのメッセージとともに、中尾先生の講演は締めくくられました。
※日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021

質疑応答では、嚥下食の栄養を強化する方法ついて質問が寄せられ、水の代わりに栄養調整食を加えることで美味しさと栄養価を両立する工夫が紹介されました。そのほかにも、調理が難しい食材や調理をする上での工夫について、嚥下食コースを考案した西田シェフにたくさんの質問が集まり関心の高さが伺えました。
第2部のイベントを終えた感想を参加者に聞いてみるとー
「今回のような嚥下食を外食で選ぶことが出来たら、嚥下障害がある方やご家族の外食機会が増えると思いました。」
「嚥下食が、健康や介護、福祉の面だけでなく、美食や経済面の多方面からも注目されるようになってほしいです。」との声が。
嚥下食の試食から講演、実習に至るまで、学びと発見の詰まった第2部。
参加者の皆さんは日々の実践に活かすヒントを得られたようです。イベントは充実した内容とともに、盛況のうちに締めくくられました。